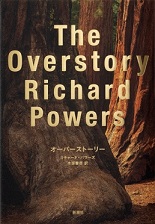次々に新作が発表される翻訳ミステリ。純然たるミステリ・ファンではない。というより、根を詰める読書の合間の息抜きとしてミステリを読む。つまらないものは読みたくないのが人情。そんなとき頼りになるのが書評サイト。その中に七人の書評家がその月の推し本を紹介するコーナーがある。そこで票を集めたのがこれ。初めて読む作家だったが、一気に読んでしまった。リーダビリティの高さは保証する。
すぐにカッとなる元女性刑事と人嫌いの劇作家が繰り出す丁々発止のやりとりが、一時期ハリウッドで流行ったスクリューボール・コメディを思い出させる。出会いがこれだけ険悪だと、最後はハッピーエンドに終わるんだろうな、と誰でも想像がつく。問題はこれがミステリだということ。謎解きの第一は宝さがし。死んだ天才画家の遺作をみつけだせ、というもの。しかし、その謎は途中で解け、新たなミッションが。死んだはずの子は生きているのか。
そもそもの発端は、画家の遺産を管理する画廊オーナーが、パリにある画家の旧宅を貸し出したことにある。ネットの不具合で、元刑事のマデリンとアメリカ人の劇作家ガスパールにダブル・ブッキングが生じたのだ。どちらも一目でその家が気に入り、互いに譲らぬ二人。マデリンは画廊オーナーのもとを訪れ解決を求めるが、担当者は不在で目途が立たない。逆にオーナーから画家の遺作を探してもらえないかと提案される。
ショーン・ローレンツはビルの壁や地下鉄にスプレーで絵を描くペインターだったが、ある日目にした美女に一目惚れ。至る所にその姿を描くという挙に出る。それが話題を呼び、画廊オーナーの勧めもあって活動の場を美術界へと転ずる。やがてペネロープと結婚し、天才画家の名をほしいままにするが、ニューヨークで開かれる個展のために訪米中、母子が拉致され、妻の目の前で息子が殺されるという悲運に見舞われる。
画家はそれ以来絵筆をとることなく、身も心もぼろぼろになり、遂には路上で果てる。死の直前、画廊のオーナーに遺作があることを告げたのだが、それがどこにあるかは言わず、謎めいたメッセージだけを残していた。マデリンが依頼されたのは、その遺作を見つけることだった。彼女には世間をにぎわした事件を見事解決に導いた過去があったからだ。
愛する者と別れることの苦しみを、仏教では「愛別離苦」という。息子を失う悲しみ故に死ぬのはショーンだけではない。マデリンは愛した男との間に子ができず、男は妻のもとに去る。彼女が深く傷ついたのは、再会した男の傍に少年がいて、二人に子どもができたらつける筈だった名前で呼ばれていたことだ。自死を試みるも失敗し、精神科の厄介になり、今も回復できていない。マデリンは立ち直るため、自分の子を持つことを欲していた。
ガスパールには父を自殺に追い込んだ負い目があった。両親の離婚後、彼は母に引き取られた。父とは週に一度面会が許されていたが、父子は母の眼を盗んで何度も会っていた。自分の失言でそれを母にとがめられ、裁判所から接見禁止を言い渡され、父は自殺した。彼が人嫌いやアルコール中毒になった遠因はそこにあるのかもしれない。彼は息子を失ったことで死に至ったショーンに父を重ねてしまう。
表面上は激しくぶつかり合うが、二人には深く傷ついていて、精神的には死にかけているという共通点がある。これは、そんな二人が画家の遺作を探し、そこに隠されていた「ジュリアンは生きている」というメッセージを解読し、画家の息子の生死の確認を果たすことを通じて、自分たち自身が今いる「死」の状態から「再生」を果たす「死と再生」の物語でもあるのだ。
事実、文明の利器を嫌悪し、スマホもネットもいじらないガスパール。長髪に髭を伸ばし放題にし、ランバージャック・ジャケットに身を固めた男は、謎解きに入ると同時に別人に変わる。あれほど飲んでいた酒を断ち、髪を切り、髭を剃り、画家がアトリエに残したジャケットに着替え、スマホを買い、ネット検索まで始めるようになる。まあ、こうしないと、二人の主人公が代わる代わる視点を交代し、同時進行で事件を解いてゆく、この小説の構成が成立しないということもある。が、それにしてもこれを「再生」といわず何という。
この話は、明暗が対比的に扱われている。マデリンとガスパールが生きている現代は、喧嘩や言い争いは絶えないものの喜劇的な要素に満ちている。反対に、過去の事件に纏わるすべてが暗く惨たらしく悲劇的だ。小児虐待、育児放棄に対する報復、身を捨てて尽くした相手の手にした幸福に対する激しい憎悪。簡単には殺さず、精神的に痛めつける嗜虐的な犯人像、とどこまで行っても救いがない。
舞台をパリにとった前半はスクリューボール・コメディ・タッチ。過去のニューヨークの事件を追う後半は人間の心理の残酷さや複雑さを追求する、サイコ・スリラー・サスペンスのタッチ。すべては、次々と現れる意外な手がかりに導かれるように、作家の操る筆に身をゆだね、あれよあれよと結末に行き着く喜びを味わうことに尽きる。明―暗―明と過去の暗いトンネルを抜けて明るい現在に立ち戻ったときの解放感が心地よい。陰惨な過去があるからこそ再生を果たした今の明るさが引き立つ。騙されたと思って読んでほしい。