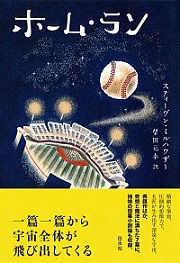ウィリアム・トレヴァーの絶筆「ミセス・クラスソープ」を含む、文字通り最後の短篇集。トレヴァーのファンなら誰でもすぐに手に取って読もうとするはずだから、こんな駄文を弄する必要もない。だからといって、初めての読者にぜひ読んでほしいと勧めようとも思わない。多分、とっつきにくいと思うから。はじめてトレヴァーの短篇集を読んだときは、首をひねった覚えがある。それまで読んでいた外国文学と少々趣きがちがったからだ。
派手なところはないが、落ち着いているとも言い難い。ひねった言い回しではないのに、妙にとらえどころがない。一読したところ、書いてあることは理解できるのに、全部わかったとは思えない。つまるところ、自分には合わないのだと思った覚えがある。ところが、それからしばらくして、トレヴァーの別の短篇集を読んでみたところ、これには興趣を覚えた。いったいどういう訳なのか。何冊か読んでから、最初の本を再読したら、初読時とは印象が全然違った。どういうことだろう。
短篇小説の定義を問われ、トレヴァーはこう答えている。
それは一瞥の芸術だと思います。長篇小説が複雑なルネサンス絵画だとしたら、短篇小説は印象派の絵画です。それは真実の爆発でなければならない。その強さは、絵に盛り込まれたものと同じくらい――それ以上ではないにせよ――そこから削られたものに負っています。短篇小説においては無意味なものを排除することが重要です。ただその一方で、人生はほとんどの部分が無意味なのですけど
小説の中で、人物の抱える「真実」の爆発する強さが、そこに盛り込まれたものより、そこから削られたものに負う、というのがまさにそれだと思う。ふつうの作家の小説は過不足なく書かれていればいい方で、強さを求めてあれこれと盛り込みすぎるきらいがある。そうする方がいいと思うからだろう。違うのだ。トレヴァーの言う通り「人生はほとんどの部分が無意味」なのだ。でも、人生のほとんどが無意味だなんて誰に分かるだろう。
トレヴァーの作品で主人公をつとめるのは、ほとんどが無名の市井の人々である。そういう人々にとって、ほんとうに意味のある人生の瞬間とは、そう度々あるとも思えない。自分の人生を振り返ってみても、日々はほぼルーティンの繰り返しだ。わざわざ取り出して見せるワンカットなど見つかりそうもない。しかし、誰にだって人生の中で一度くらいは「真実」が爆発する時があるにちがいない。それをどう切り取ってみせるかが短篇小説作家の力量なのだろう。
しかも、盛り込むことにではなく、無意味なものを削ることなくして、トレヴァーの短篇は生まれない。はじめて読んだときに感じた分かり難さは、そこにあった。ここぞという場面に強度を与えるため、トレヴァーはあえて省略する。トレヴァーを読むとは、与えられたものを手がかりに、省略された部分も読むということだ。気楽に構えて読んでなどいられない。うかうかしていると大事な一文を読み落とす危険がある。
ミステリを読んでいて、ちらっと書かれていたことが大事な謎を解くカギになっていた、と気づかされることがある。再読すると、ちゃんと触れられていて、よく読めば自分にだってわかったはずじゃないか、と思ってしまうが、そうではない。よく読めば分かるが、普通に読んだだけでは分からないように作者は気を配って書いているのだ。トレヴァーの短篇はミステリではないが、書かれていないものが謎のように働くことがあり、最後になってはじめて分かることもある。
「ピアノ教師の生徒」は、素晴らしい芸術家とその人間性の関係を主題に、人は誰しも自分を基準にしてものを見ることから逃れられないという真実を見つめた一篇。足の不自由な男」は、賃仕事を求めて人の寄りつかない一軒家にやってきた二人が豹変した夫人の態度をいぶかしむという「ミステリの味わいがある。「カフェ・ダライアで」は、一人の男をめぐって仲たがいした旧友の女二人。一度ひびの入った関係を修復することの難しさをじっくり見つめている。
「ミスター・レーヴンズウッドを丸め込もうとする話」は、若い女を食事に誘い、自宅に連れ込んだ裕福な銀行の顧客から金をせびろうとする話。高級住宅地まで来てはみたものの女の心は揺れるばかり。「ミセス・クラスソープ」は、妻に先立たれた男と年上の夫を亡くしたばかりの女との出会いとすれちがいを異なる視点で描いてみせる。人生の哀感を抑制の効いた筆致で描き出す。「身元不明の娘」は、不自然な死を遂げた孤独な娘の生活背景が最後の最後まで明かされない、という焦らしの効果を狙った作品。
「世間話」は妻子ある男性に勝手に思いを寄せられて、夫を返せと妻に非難され、困惑する女だが、実は女にも秘められた悲話があった。記憶障害を持つ絵画修復士と娼婦の一夜の出会いの奇跡を描く「ジョットの天使たち」。荒野(ムーア)を舞台に男と女の運命的な出会いと別れを描いた「冬の牧歌(イデイル)」。寄宿学校に入った娘とその父親の物語と役所を早期退職した二人の女の物語が交互に語られ、それが最後に交わることで、娘の出生の謎が明かされるミステリ仕立ての「女たち」、と最後まで、衰えをみせなかったトレヴァーの筆力が窺える、どれも読みごたえのある全十篇。