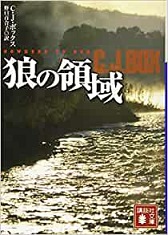ミステリの世界には、いろんな刑事や探偵がごろごろしている。新しい主人公を考える作家も大変だ。四肢麻痺で首から下が動かせない、リンカーン・ライムは画期的だったが、さすがに、行動に制約が多すぎて作家の方にもストレスがかかったのか、今度の主人公は、サバイバル術に長けた行動派だ。おまけに、職業は刑事でも探偵でもない。なんと「懸賞金ハンター」だというから、いつの時代になってもアメリカは西部劇から抜けきれないらしい。
とはいえ、凶悪犯を狙う「賞金稼ぎ(バウンティ・ハンター)」ではない。行方不明者を見つけるため、個人や警察が懸賞金を設けることがアメリカにはあるようだ。というのも、もしそれが誘拐事件なら早期解決が大事だが、警察は実際に何かが起こるまでは動き出さない。そこで、こういう仕事が成り立つわけだ。仕事は失踪人の居場所を見つけるところまでで、救出はしない。後は警察の出番というのが建前だが、警察の動きは遅い。そこで、自ら事件の渦中に飛び込むことになる。
名前はコルター・ショウ。シェラネバダにある「コンパウンド(地所)」という広大な土地で父のアシュトンからサバイバル術を訓練されて育つ。兄妹の中でもコルターは追跡がいちばん得意だった。大学を優等で卒業し、一時は弁護士になることも考えたが、しばらく事務所勤めをしてみて、自分には向いていないことが分かった。一つところにとどまるのが苦手だったのだ。今ではウィネベーゴのキャンピング・カーを駆ってどこへでも出かけて行く。
ヤマハのオフロードバイクも積んでいるが、仕事中はウィネベーゴを近くのRVパークに停め、黒か紺のレンタカーを借りて行動する。なかなかの美食家で行く先々の地ビールを楽しみ、コーヒーはエルサルバドルの豆に決めている。今回はメキシコの朝食向け卵料理、ウェボス・ランチェロスのトルティーヤをコーン・ブレッドに変えて食べるという試みをしている。多分行き先が変わるたびにそこの地ビールと名物料理が紹介されるのだろう。こういう設定が心憎い。
第一話の舞台は、シリコンヴァレー。十九歳の女性が失踪し、父親が懸賞金を設けた。額は一万ドル。高額ではないが、父親の切羽詰まった様子を聞いて引き受けた。まだ明らかにはされていないが、ショウには別の稼ぎがあるらしく、懸賞金で食べているのではないようだ。ショウの捜査方法は特に目新しいものではない。聞き込みをして、目撃情報を集め、立ち回り先を突き止める。何しろ、まだその時点では事件かどうかも明らかではないのだ。それに警察ではないショウにできることは限りがある。
ただ、追跡者としての能力には秀でている。今回はカフェの監視カメラに残っていた映像から、行き先を予測し、事件現場で格闘跡を発見し、被害者の携帯電話を発見する。それで一件楽着のはずだった。だが、いくら待っても警察は来なかった。仕方なく、周囲を探るうちに死体を隠すにはうってつけの廃工場を見つける。そこで事件に巻き込まれることになる。犯人は現場に隠れていて、ショウを襲ったのだ。
誘拐事件が起きても身代金について犯人からの要求はない。しかも、一件だけでなく同一犯と思われる誘拐監禁事件が連続して起こる。カフェのコルクボードに残されていたステンシル風の男のイラストから、ショウはそれが「ウィスパリング・マン」というゲームの登場人物であることを知る。当時サンノゼで大規模なゲーム・ショーが開催中で、大勢のゲーマーでシリコンヴァレーは賑わっていた。犯人の狙いはゲームに関わりがあるらしい。
三件の誘拐監禁事件は「ウィスパリング・マン」というゲームを模したものだった。ホーム・スクーリングで育ったショウはゲームに疎かった。そこで、業界人がショウにレクチャーするという形式でゲームに関する蘊蓄が語られる。しかし、ゲームに詳しい読者には不要だろうし、ゲームをしない者には退屈な蘊蓄だ。謎解きミステリにはよくこうした解説が登場するが、ミスディレクションに必要なのだろうか。
同業者によるゲーム開発企業に対する妨害か、ソシオパスによる犯罪なのか、犯行動機ははっきりしないが、ゲーム中毒者の犯行なら、犯行の起きていた時間はディスプレイから離れていたことだけははっきりしている。「ウィスパリング・マン」を配信している会社社長の協力を得て、これだろうと思われる人物を特定するが、果たして最後の被害者を生きているうちに救出することができるのだろうか。
捜査権のないショウには警察関係者の協力が必要だ。今回は対称的な二人が登場する。いかにも刑事という見かけの白人刑事ライリーとアフリカ系アメリカ人の女性刑事スタンディッシュがそれだ。ライリーは女性の巡査にセクハラまがいの発言を繰り返す嫌な刑事役を演じ、スタンディッシュは逆に有能で感じのいい刑事役だ。この二人の役割設定がうまく生きていて、シリーズ物ながら、主人公がキャンピング・カー暮らしという設定では、おそらく、二度と登場しないのが惜しいくらい。
ジェフリー・ディーヴァーといえばどんでん返し。今回もきっちり用意されている。しかも、そのうちの一つは、ショウの抱えている難問についての謎解きの一つに関わるものだ。ショウは死んだ父が何か秘密を抱えていたことを知っており、シリーズを通してその解決を図ってゆくことになる。広大な土地でのホーム・スクーリングやサバイバル術の訓練といった、ショウの生い立ちが普通でないのには何か理由があるのだろう。次回作が楽しみな新シリーズの幕開けである。