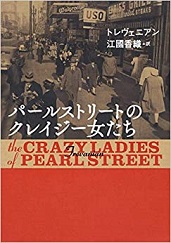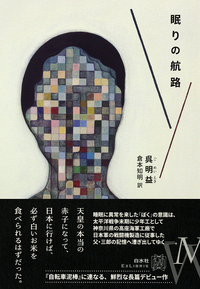ローレンス・ブロックの名を知ったのは彼の編集した『短篇画廊』がはじまり。続編の『短篇回廊』を読み、その実力のほどを知った。そして、三巻本の『BIBLIO MYSTERIES』の序文で杉江松恋氏が、ローレンス・ブロックの作品として挙げていたのが、本作と『泥棒はライ麦畑で追いかける』の二作だった。チャンドラーがハメットに贈ったサイン本をめぐる話と聞いては、チャンドラー好きとしては放っておくわけにはいかない。
泥棒探偵バーニイは人気があるらしく、これがシリーズ八作目。盗みに入ったところで殺人事件に遭遇し、しかたなく素人探偵として事件の謎を解く、というのがお約束らしい。シリーズ物の常として、マンネリズムは楽しみながらも、過度のマンネリ化を避けるため、一話ずつ趣向を凝らさなくてはならない。今回のそれは、クリスティの『ねずみとり』と『そして誰もいなくなった』を足して二で割る、本格英国ミステリ調の道具立て。そこにレイモンド・チャンドラーをからめようという、何とも凄い力業である。
ニューヨークで本屋を営むバーニイは、イギリスをこよなく愛する恋人のレティスを喜ばせようと、カトルフォード・ハウスに予約を入れていた。そこは、イギリス風のもてなしで有名なカントリー・ハウス風ホテルで、今では本国でも望めないサーヴィスが受けられることで知られていた。ところが、直前になってレティスが結婚することを知ったバーニイは、キャンセルする代わりに、友人のキャロリンを誘う。彼女は、宿賃はおごりだと聞き、同行を承諾する。
実はバーニイには別の狙いがあった。カトルフォード・ハウスには図書室があり、多くの貴重な本が収蔵されている。その中に、チャンドラーがハメットに贈ったサイン本の『大いなる眠り』の初版本があるらしい。もし、ダスト・カバーつきの美本なら二万五千ドルはくだらない代物だ。そんな所に一人で泊まりに行けば、不審に思われるのは必定だが、二人連れなら疑われることもない。そういう算段でキャロリンを誘ったのだ。彼女はレズビアンで、そちらの心配はなく、バーニイが泥棒だということも知っている。この二人の気のおけない会話が実に気が利いていて、楽しい。
ところが、ニューヨークから北に三時間ほど行くと、三月だというのに雪が降りだし、カトルフォード・ハウスに行くには、断崖にかけられた吊り橋を徒歩でゆくしかない。予想通り、泊り客が全員揃ったところで、この吊り橋は切れ落ちる。おまけに雪で電話は通じなくなる。完全なクローズド・サークルの完成である。それから、一人、二人と死者の数は増え、連続殺人の様相を呈することに。やむを得ず、バーニイが素人探偵を買って出る。だが、決定的な証拠がつかめないバーニイは、自分の考えを披歴することをためらい、またもや新たな死者が出る。
雪に降り込められた、英国風カントリーハウスで起きる連続殺人、という見立てである。本屋でもあるバーニイは、いやというほどミステリを読んできている。それで、ついついクリスティ風ミステリに倣い、謎解きを始めるがなかなかうまくいかない。何かがちがうのだ。そこで、彼が思いついたのは、これは、クリスティではなく、チャンドラーなのでは、という考えだ。ポアロやミス・マープルのやり方で行くのではなく、フィリップ・マーロウのように行動してみることだ。
まあ、キャロリンもいうようにどこがマーロウ、という感じではあるのだが、真相は究明される。いわゆる謎解きが主体の本格物を好む読者にとっては、少々というか、全くというか、謎解きはかなり物足りない、と思われる。だが、ローレンス・ブロックの泥棒探偵バーニイ・シリーズを楽しみにしている読者には、その辺はまったく問題ない。最後に、とっておきの解説がついている。チャンドラーの読者なら、よく知っている、あの「運転手を殺したのは誰だ」というエピソードである。
『大いなる眠り』が映画化され、脚本の手直しをしているときのことだ。スタッフの一人が登場人物の一人であるお抱え運転手がどうして死んだか知りたいと言い出した。誰も分からないので、作家に聞いてみようということになった。そこで電話したところ、チャンドラーは「わからない」と答えたという、文学史上超有名なエピソードである。キャロリンもいうように、イギリス風の謎解きミステリでは、謎は最後にきちんと解かれるものと決まっている。バーニイが最後に言う。
「現実社会というのは、もっと不確かなもので、わからないことももっといっぱいある。わからないというのは、確かに苛立たしいことではあるけど、だからといって、そのために夜も眠れなくなるというほどのものでもない。だろう?」。これは作者、ローレンス・ブロックによる正統的謎解きミステリに対する批評ではないだろうか。その手の作品の中には、辻褄を合わせるために、かなり無理をした作品が少なくない。そんなことより、もっとミステリを愉しむことだ。本作のケリのつけ方には、フィリップ・マーロウのスタイルが感じられる。本格物のパロディよろしく、面白おかしく洒落のめしながら、そのあたりはきちっとハードボイルドをやっているのだ。憎いね、ローレンス・ブロック。