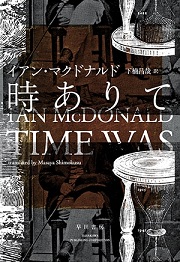「二〇〇〇年のある日、ローリー・スチュワートは故郷のスコットランドを散歩していて、ふと、このまま歩き続けたらどうだろう、と考えた。それがすべての始まりだった。その年、彼はイランを出発し、アフガニスタン、インド、パキスタンを経由しネパールまで、アジア大陸を横切る全長九六〇〇キロを踏破する旅に出た(「訳者あとがき」より)」
だが、タリバンに入国を拒否され、アフガニスタンは後回しにするしかなかった。翌年にタリバン政権が倒れると、彼は大急ぎでネパールから引き返してきたのだ。
通常アフガニスタンの西の都市ヘラートから東のカブールに行くには、ヒッピーたちが旅したように南のカンダハールを経由する。それなのに、あえて最短距離のルートを選択し、積雪三メートルに及ぶ冬の山岳地帯を抜けて歩き通した苛酷な旅の記録だ。誰からも冬季に山岳地帯を行くのは無謀だと説得されるが、南はまだタリバンの勢力下にあり、そこを通るのは危険だ。彼は一刻も早く踏破したかった。歴史学者でもある男はムガール帝国初代皇帝バーブルの日記を通して、彼が同じルートを冬に踏破したことを知っていた。
邦題には「犬と歩く」とあるが、はじめは犬は登場しない。その代わりに武器を携行した男三人が旅のお伴だ。なにしろ、タリバン政権が崩壊してたったの二週間だ。外務官僚のユズフィは言う。「きみはアフガニスタンの観光客第一号だよ。(略)護衛を連れて行きなさい。これは譲れない」。彼は市場で手ごろな木の棒を買い、鍛冶屋に行って両端に補強用の鉄を取り付けてもらう。この杖は「ダング」と呼ばれ、山道を歩くとき重宝するが、いざというときは武器にもなる。
この本のことは、ロバを連れてモロッコを旅している邦人のツイッターで知った。本の影響を受けてのロバ旅らしい。モロッコではマカダム(村長)が行く先々についてきて、次の村まで同行し、そこのマカダムに引き継ぐ。イスラム教の喜捨の精神で、旅人は大事にされるのだ。この本のなかでも、日が暮れて村に着いた旅人は一夜の宿と食事を提供され、翌日次の宿を紹介してもらって旅を続けている。一日の旅程が終わる頃には次の村で休めるようになっている。今は荒れ寂れているが、かつては通商のために人が通った道なのだ。
もっとも、当時のアフガニスタンは、まだ各地でタリバンが戦っており、宗派間、部族間の抗争も続いていた。武器を携行した男たちが同行していては、村人も投宿を拒否できまい。喜捨といえるのかどうか。食事といってもパンとお茶がやっとで、時にはパンさえ出ないときもある。どの村も貧しく自分たちが食べるのもやっとなのだ。旅はおろか、女たちは村から離れることができず隣村のあることさえ知らない。
そんななか、泊まった一軒の家で、犬を連れていけと勧められる。大型のマスティフ犬の一種で、オオカミ対策に飼われているという。ただ、餌代にも事欠く有様で、彼が貰ってくれれば餌にもありつけるだろうという。彼はためらったすえ、その犬を引き受ける。皇帝にあやかって「バーブル」と名づけられた、この犬がいい。イスラム教の国では、犬は不浄な動物とされ、ペット扱いされない。ただ使役されるだけだ。当然、犬の方も飼い主に愛着も示さなければ、遊びにつきあうこともない。だが、スコットランド人はちがう。
はじめは居場所を離れることを嫌がり、歩き出してもすぐに地べたに座り込んで動こうとしない。パンで釣ったり、紐を引っ張ったりしてやっと動き出す始末。ところが、そんなバーブルが少しずつ彼に心を開き出す。雨や雪の中を苦労して歩き、村にたどりつくと、彼は嫌がる村人に頼み込んで、犬をどこか屋根の下で寝させてくれるように頼む。それをすませるまで自分も家の中に入ろうとしない。食事に肉が出ると、犬にも分けてやる。旅が終わったら、スコットランドに連れ帰るつもりでいる。
どこを向いても厳しい自然と貧しい人々の暮らしがあるばかり。そんなある日、険しい山の中で尖塔を発見する。伝説の「ジャムのミナレット」だ。「細かい複雑な彫りの施されたテラコッタにターコイズブルーのタイルが線状にはめ込まれた細長い柱が、六〇メートルの高さにそびえている」。塔の首のあたりにはペルシアンブルーのタイルでこう綴られている。「ギヤースウッディーンはヘラートにモスクを、チスティシャリフに修道僧のドームを建て、失われた都ターコイズ・マウンテンをつくったゴール帝国のスルタンだ」
彼はその辺り一帯の司令官の家に誘われ、塔についての話を聞き、地中から掘り出したものを見せてもらう。何人もの考古学者が訪れながら、遂に発見することのできなかった、失われた都ターコイズ・マウンテンの遺跡は、盗掘者の手で掘り出され、二束三文の値で売り飛ばされていた。かつて、チンギス・ハーンに焼き尽くされた伝説の都は、ずっとイスラムの遺跡として守られてきた。しかし、タリバンが追いやられた今、僻遠の地ということもあり、新政府の目も及ばず、せっかくの文化遺産は荒らされ放題になっている。
地下に貴重な文化遺産を蔵しながら、ヤギが食べる草も生えない高地に暮らす人々は、掘り出した遺物を売って暮らすしかない。皮肉なことだ。遺跡を見る目は歴史学者のそれで、この部分は明らかに他とは筆致が異なる。だが、その後、旅は苛酷になる。赤痢に罹り、下痢で体力を奪われながら雪の山道に踏み迷う難行が待っていた。さすがの彼も凍った湖を行く途中で力尽き、もうここで旅を終えてもいい、と雪の中に倒れ込んでしまう。彼を救ったのはバーブルだった。首に吐息をかけて起きるよう促すのだが、それでも動かないでいると、歩いて行って振り返り越しに一声吠える。その姿に彼は自分を恥じ、再び立ち上がる。
バーミヤンの石仏が象徴するように、過去に偉大な文化を擁しながら、行路にはかつてを偲ぶよすがとてない。荒れ寂れて人も通わぬ道も、かつては隊商が駱駝に乗って通った道である。歴史家として彼はそこに何を見ていたのだろう。果たして人類は成長したといえるのだろうか。著者は声高に語ることはないが、書かれたものを読めば、その思いは読者の胸に迫る。淡々とした筆致で綴られた手記には、最後に物語のような思いもかけない幕切れが待っている。この旅に出ることで、彼はバーブルと出会うことができた。これを縁といわず何といえよう。原題“The Places in Between ”を『戦時のアフガニスタンを犬と歩く』とした訳者の思いがわかる気がした。