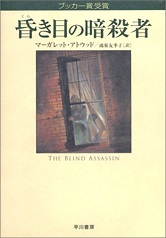
『昏き目の暗殺者』という表題は、作中に登場する二十五歳で夭折したローラ・チェイスの死後出版による小説のタイトルである。小説の中で売れない物書きの男が女にお話をせがまれて頭の中の小説を話して聞かせる。ウィアード・テイルズのような、扇情的な表紙のパルプ・マガジンに出てくる、目の見えない少年の暗殺者のことだ。その恋人は舌を切り取られてしゃべることができない少女。何やら暗示的ではないか。
所謂「入れ子構造」になっている。導入部に置かれた物語の中に、別の物語が入り込む形式のことだ。『千一夜物語』のような、といえば分かってもらえるだろう。ローラの書いた小説の中で、密会のたびに男が語る物語が勝手に羽根を広げ、想像の限りを尽くしてありえないディストピアを現出する。しかし、それらはすべて現実の世界を反映していることは必至で、読者はそれを手掛かりに謎を解いていかなければならない。
冒頭に関係者の死亡記事が引用されている。ローラ、その義兄、姪、叔母の死亡を告げる記事だ。高齢で死んだ叔母を除けば、三人は若死に、自殺を疑わせるようなところもある。これらの死の謎を解くというミステリ仕立ての小説でもある。小説の語り手をつとめるのはローラの姉のアイリス。今は亡き大工場主リチャード・グリフェンの未亡人。関係者のほとんどが他界した今、故郷で一人暮らしをする八十代の老女である
アイリスにはインドに行ってから消息が絶えたサブリナという孫がいる。たった一人の跡継ぎに、我が家の歴史を物語るという体裁で、震える手で黒いボールペンを手にして書き綴られたのがこの文章ということになる。しかし「あなた」と呼びかけられる相手は常に孫とは限らない。昔、頼りにしてた家政婦のリーニーの娘マイエラに変わることもある。もしかしたら読者ということもある。死後、誰がこの文書を読むのかは死者に分かるはずがない。
老いさらばえた「わたし」だが、文面を読む限り、したたかな意地悪婆だ。シニカルかつ辛辣。マイエラの夫で大工仕事や運転手役を務めるウォルターには心許しているふしがあるが、それ以外の周囲の人々を見る目はかなり手厳しい。記述はユーモラスなのだが、毒がある。それも半端ではない大量の毒を撒き散らすのだ。これを共感して読むにはかなりの努力がいる。語り手にも主たる登場人物にも共感できそうにないからだ。作者がリーニーとウォルターを創造しておいてくれたのが僅かな救いだ。
小さい頃に母を亡くし、戦争から帰った父は心身に傷を負い、一人塔屋の小部屋で酒浸り。リーニーという家政婦が何くれと世話を焼いてくれるものの、三つ下の妹は、言われた言葉を字義通りに受け止めてしまう「変わった子」で、両親から面倒を見るように頼まれた「わたし」には荷が勝ちすぎた。しかし、祖父が創設した釦工場がうまく運営されていた少女時代は、まだまだ幸せな時代といえるだろう。
問題は工場が経営難に陥ってからだ。父が頼ったのは競争相手であるリチャード・グリフェンという大工場主。働き盛りの独身男に十八歳になったアイリスを人身御供として差し出すことで経営を支援してもらう約束だった。ところが、二人が豪華客船で新婚旅行に出ている間に、工場は奪われ、失意の父は死んでしまう。親を亡くした十四歳のローラは、一人で自活もならず、リチャードの家に引き取られることになる。
このリチャードという男が悪党で、その妹のウィニフレッドが兄に輪をかけた食わせ物。アイリスが世間知らずなのをいいことに、妻宛ての電報や手紙を勝手に破棄し、本当のことを知らせない。だから、父の死に目にも会えず、妹が精神病院に運ばれても会わせてももらえない。姉が妹に再会するのは、リーニーの手配で救出された後である。共感できないというのは、こういうところで、いくらなんでもそこまで夫の言いなりになっていられるものだろうか。実の妹ではないか。
これは「信頼できない語り手」という手法ではないだろうか。人は誰しも自分をよく見せかけようとしてうわべを取り繕う。夫と年上の義妹を徹底的に悪者に仕立て上げ、妹に対して冷淡であった自分の過去から目を背けているのではないか。もしかしたら、世間知らずで人を見抜く力のなかったアイリスには、見ていても見えなかったのかもしれないが。
小説の中では「わたし」が昔とはすっかり様変わりした今の町を悪態をつきつつ彷徨する様子が辛口エッセイ風の文体で紡がれ、そこから過去の「わたし」の回想視点に移行するのだが、その中に時折、現在の「わたし」の視点が挿入されることで、過去は批判的に解釈され、懐疑的な思案が混じり込む。回想視点の「わたし」が「信頼できない語り手」であることを、今の「わたし」が読者にそっと目配せしているのだろう。
それでは真実はどこに書かれているのか。無論、挿入されている二重の入れ子状の物語の中にである。『昏き目の暗殺者』は誰かに追われる男と、夫のある身で密会を続ける女の逢引きをハードボイルド・タッチで描いた小説。男はその昔、姉妹の前に現れた共産主義者の流れ者、アレックスのその後の姿を彷彿させる。工場への放火犯と疑われた時に逃亡を助けたくらい、姉妹はアレックスのことが好きだった。
女にせがまれて男が語る構想中の小説のあらすじが、トカゲ男が登場する異世界ファンタジーで、豊富なアイデアが惜しげもなくばら撒かれている。ファンタジー好きの読者なら涎を垂らすところだ。異次元世界という設定だが、その背後に、二つの大戦、世界恐慌、共産主義の躍進、ヒトラーの擡頭、といった当時の世相に対する批判、不安、否定、それと同時に暗殺、大量殺戮、クーデターといったものに対する暗い愛着もまた透けて見えている。
零落した元資産家令嬢が書き遺した一家の年代記と読むもよし、家族の隠された秘密を暴く暴露小説と見るもよし。贖罪の書とも、ゴシック・ロマンスとハメット風ハードボイルド小説、異世界ファンタジーがまちがって一冊に閉じられた乱丁小説とも読める。これ一冊の中にこの世界にありとある物語、詩、小説を封じ込めてやろうという作家の執念を見る思いがする。マーガレット・アトウッド渾身の一冊。
原題は<The Blind Assassin>。普通なら「盲目の暗殺者」だろう。<blind>に「昏い目」という訳をあてているところが、なかなか意味深だ。「黄昏」に使われているように、「昏」には「日が暮れてくらい」という意味がある。それと同時に「昏迷」のように「物の道理が分からない」という意味でも使われる。見る目さえあれば見える程度にはまだ光が残っている状態が「昏い」のであり、見えていても、それが分からないことを「昏い」というのだ。手練れの翻訳家、鴻巣友季子ならではの名訳。