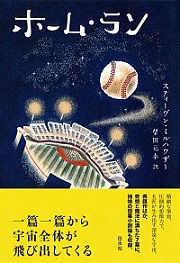ジョン・ル・カレは、映画にもなった『寒い国から帰ってきたスパイ』、『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』(邦題『裏切りのサーカス』)、『誰よりも狙われた男』等々、数々の傑作をものしてきたスパイ小説の大家である。作家になる前は英国諜報機関MI5に入り、後にMI6に転属、二等書記官として旧西独大使館、ハンブルクの総領事館に赴任した経験を持つ。
自身の経験や見聞、取材に基づいた事実をもとにストーリーを組み立て、複雑なプロットを駆使し、一筋縄ではいかない込み入った状況を巧みに操る力を持っている。冷戦が終了したとき、これでスパイ小説は終わった、と誰もが思った。が、どっこい、その後もル・カレはしぶとくこのジャンルに留まっている。キム・フィルビー事件を素材にとった『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』、イスラム過激派を扱った『誰よりも狙われた男』と、時代は変わっても、人間にとって国家が存在し続ける限り、題材には困らない。
本作の舞台はEU離脱に揺れるイギリスの首都ロンドン。主人公で語り手でもある「私」はナットと呼ばれる、イギリス情報局秘密情報部に勤める有能な要員運用者(エージェント・ランナー)。しかし、四十代後半ともなれば、現役のスパイではいられない。デスクワークの嫌いな彼は引退も覚悟していた。そんな彼に用意されたポストは<安息所>(ヘイヴン)と呼ばれる本邦内のロシア支局で、彼に言わせれば「ロンドン総局の管理下にあるまったく機能していない下部組織で、再定住させた無価値の亡命者と、落ち目の五流の情報屋をまとめて捨てる廃棄物処分場」だ。
そんなところで、一つ拾い物があった。最近加わったメンバーでフローレンスという若い女性だ。そのフローレンスが立てた<ローズバッド>作戦が彼の目にとまったのだ。ロンドン在住の新興財閥(オリガルヒ)のウクライナ人がモスクワ・センターとつながっていて、その怪しい資金の出所を探るというものだった。怖いもの知らずで、作戦の提案書にも道徳的な怒りをたぎらせずにはいられないフローレンスは、本署でも重要な役が任されている。
話は変わる。ナットは運動好きでバタシーにある<アスレティカス・クラブ>のバドミントンのチャンピオン。そんなナットにある晩、エドという青年が試合を申し込みに来る。実際戦ってみると両者の腕はほぼ互角で、いい好敵手だった。気のもめる仕事の息抜きに最適な相手を見つけたナットは土曜の夜にエドと力の限り試合し、その後いつもの場所でラガーを飲んで雑談をするのを楽しみにしていた。エドの関心は、現在の世界が置かれた状況についてで、特にEUを離脱しようとしているイギリスとそれを煽るトランプに腹を立てていた。
それはエドの求めでダブルスの試合をした夜のことだった。妹のローラがバドミントンをしたいと言っている、ついては誰かバドミントンのできる女性を知らないか、というのがエドの頼み。フローレンスに訊くと難なく了承してくれた。試合後、四人で食事に行くところで、電話が入った。<ヘイヴン>からで、休眠中の工作員から至急来てくれと連絡があったという。要員からの依頼は断れない。「私」は三人と分かれ、ヨークに向かう。
休眠工作員はセルゲイといった。ずっと音沙汰のなかったモスクワから連絡が入った。ロシアの大物スパイがロンドンに現れるという。ついては<隠れ家>を用意せよというもので、それは完璧主義を絵に描いたような注文だった。「私」はある人物を思い出し、過去に要員だった男に会いにチェコに出向く。それで確信を得た「私」は、これが活動中か今後活動しうる貴重なイギリス人情報源を含む高度な諜報活動であり、モスクワ・センターの非合法活動の女王自らが采配を揮っていることを突き止める。その人物とイギリス人情報源と出会う日が来た。観光客や市民に扮した大勢の監視員が見守るなか、そこに現れたのは誰あろう、「私」がよく知る人物だった。
巧みに張り巡らされた伏線が一つ、二つと回収されていくと、あっと驚かされる風景がそこに現出する。本格的なスパイ小説でもあり、無類のサスペンス小説でもある。どこかで誰かに罠にはめられたのか、疑心暗鬼にとらわれながらも「私」は与えられた手がかりを丁寧に読みほどき、耳に残る微かな訛り、アクセントを頼りに、名探偵よろしく事態を正しく読み替えてゆく。そして、最後に有能な要員運用者として、かつての相棒だった妻の手を借りながら窮地に陥った者たちの救出に向かう。
窮地に追い詰められた男が「他人を魅了する」という能力だけを頼りに、国家権力を相手に戦いを挑むという痛快極まりないストーリー。銃も拷問もなし。本人の情報ファイルにある通り「重圧の中でも多弁」という持てる資質を十二分に発揮し、かつての仲間や昔の恋人相手に、彼らの握っている情報を嗅ぎ出すあたりは息を呑む。冷酷非情というのがスパイ物のステレオタイプだったが、これは妻や子を愛する、ごくごく家庭的な人物が演じる逆転劇。シリアスな話題を扱いながら、どこかユーモアさえ漂う、後味の好い快作といえよう。